CDI �̓��쌴��
- 50V����300V�߂��܂ł��������W�F�l���[�^(���d�@)�ō��ꂽ�d�C���A�_�C�I�|�h�Ő����B
- �R���f���T�ɏ[�d����B
- �_�^�C�~���O���r�b�N�A�b�v�@(�p���T)�Ō��o�M�����ACDI�@���j�b�g�ɑ���B
- �r�b�N�A�b�v�@(�p���T)�̐M�����@SCR�̃Q�[�g������@SCR���@ON����B
- �R���f���T�ɒ~���Ă������d�C����C��SCR�ʂ��ĕ��d
- �R���f���T�ƃC�O�j�b�V�����R�C����1�������Ȃ����Ă���̂ŁA1���R�C���ɒʓd����d���������B
- �P�������Q�����̕����R�C�����R�����Ă���̂ŁA2�����Ɋ�����{�̍����̓d�������āA�X�p�[�N�v���N�J��_�����B
|
CDI �̒����ƒZ��
���@��
- �v���O�Ɂ@���Ԃ肪���������Q�T�C�N���G���W���ɂ́A���ړ_��CDI�@�_�Ε������@�ǂ��B�@
- �ȃG�l�B
- ���ړ_��CD�Ȃ�@�|�C���g�̒����s�v�B
�Z�@��
- �X�p�[�N���Ԃ��Z���B�@
- �Ԃ�₷���A�Q��ׂꂽ�B�@1��ڂ͕ۏ���Ԓ��ɍ���]�܂ŏオ��Ȃ��B�@CDI
��ւ��@�@�Q��ڂ̌̏�̓G���W�����|����Ȃ��Ȃ����B�@
- ����̗l�ɐ������~�ɂȂ�A�C�������� �B�@�f�W�^��CDI
�Ȃ�@����グ( ���̏ꍇ)
- ���M���C�ɂȂ�B�@���M�őΉ�
|
����I���W�i���@CDI �̐���
�p�ӂ��镨
- ��Ձ@�T�O*�U�O�ʂ̂��� �o�C�N�ׁ̈@�傫���ɐ��������邽�߁@�@��P�O�O�~
- SCR �@�U�O�OV�ȏ�@�W�A���y�A�ȏ�̕��@����
�r�e�W�i�y�S�V�Ȃǁ@�����������Ɓ@�����ɒׂ��ׁ@�@��Q�T�O�~
- �g�����W�X�^�@2SC1000�܂��́@2SC1815 �Ȃǁ@�R�O�~
�@�@�@
- �R���f���T �@�U�R�OV �@�O�D�S�Vu�e 2�@�@�T�O�O�~�@�@1uF�ɕύX(2008�N2��)
- �Z���~�b�N�R���f���T�@�Q�T V �ȏ�@�O.�O�Pu�e
�Q�@�O�[�q���M�����[�^�́@���U�h�~�@��S�O�~
- �t�H�g�J�v���@1�@�V���[�v�@PC817�Ȃǁ@�m�C�Y�t�B���^�[���@�≏�̈g�p�@�@��P�O�O�~
- LED 2�@�@�@�Q�O�~�@�����^�C�v�@�@
- �_�C�I�[�h�@�P�O�O�OV �@2A�ȏ㕨�@�R�@�@��X�O�~
- �O�[�q���M�����[�^�@�TV�p�@�P�@�@�@7805�@�@�P�O�O�~
- ��R�@1/4W �@�@1�O�O�I�[���@�@�P�D�QK�I�[��
�R�@�@�@�RK�I�[���@�@��Q�T�~�@
- ���c����
- �v���b�`�b�N�P�[�X�@��P�O�O�~
- �d��
- ���M�@�����P�[�X�ɑg�ݍ���Ł@�P�[�X����M�ɂ��Ă��ǂ��ł����A�≏�������ɂ��Ă��������B�@���d���܂��B
�����~������CDI�����i�Ō����A���̂��炢�̂��̂ł��B
���삷��ꍇ�A���ꕔ�i���g���Ă��܂���A���i�e�Г����悤�Ȃ��̂��o���Ă��܂��̂ŁA�����i�ł��������߂��������ƁA��ɓ�������Ȃ�܂��B
|
��Ǝ菇
- �o�C�N�̃V�[�g�Ɓ@�^���N���͂����ACDI ���j�b�g�����o���B
- �e�X�^�[�Ł@�s�b�N�A�b�v�A�C�O�j�b�V�����R�C���A�W�F�l���[�^(���d�@)
�ɁA�ُ햳�������ׂ�B
- �C�O�j�b�V�����R�C���́@�e�X�^�[�̒�R�����W�ŁA�ꎟ���@���̃R�C�����f�����Ă��Ȃ����ׂ�B�@���Ȃ݂�MTX125R�̃C�O�j�b�V�����R�C���́@�ꎟ���̒�R�́@0.2����0.4�I�[���@����3.5����4.5�L���I�[��
�ł��B
- �W�F�l���[�^(���d�@)�@�L�b�N���ăe�X�^�œd�����o�Ă��邩�ׂ�B�@�L�b�N�X�^�[�g�ނ��ƂŁA50V������@OK�B
- �����v�ޗp���d�@�̓o�b�e���[���O���A�L�b�N����12V�L��A���d�@��OK�B
- �s�b�N�A�b�v �́@�e�X�^�[�̒�R�����W�ŁA���ʂ�����ALED�݂̂��Ȃ��ŃL�b�N�X�^�[�g�ށA�u���_�������OK�@(�s�[�N�z���h�t���̓d���v��I�V���X�R�[�v�������̂ł��̕��@���̂�܂����B)�@
- �s�b�N�A�b�v(�p���T)�̓d�����ႭLED���_�����Ȃ���@�t�H�g�J�v����p�������̉�H�͎g�p�ł��Ȃ��B�@��H�ύX�K�v�B
- ��ꂽCDI ���j�b�g�̃\�P�b�g�����������O���A�\�P�b�g�̒[�q�ɓd���c�t���Ă����A��Ŏ����CDI
���j�b�g�Ɛڑ����邽�߁B
- �}�ʒʂ�ɁACDI ���j�b�g�̉�H�����ɍ��グ��B
- CDI ��H�}�ɂ��邢�����̃A�[�X�����́A��܂Ƃ߂ɂ��ā@��_�Ŏԑ̃A�[�X����B�\�P�b�g���ɃA�[�X�̐��o�Ă���ꍇ���̐��ɃA�[�X���Ă�OK�B
- CDI ���j�b�g�ƁA��ꂽCDI ���j�b�g�̃\�P�b�g���������A���O�����\�P�b�g�Ɛڑ��B
- ����CDI ���j�b�g���o�C�N�Ɏ��t����B�@�ڑ�
- �X�C�b�`�����A�L�b�N���ăX�p�[�N���Ă���̂��m�F����B�@
 ���d���� ���d����
- ��肭�|����A�܂����i�A�G���W���̉�]���グ�Ċm�F�B
- �s�b�N�A�b�v�ɂ͋ɐ�������̂ŁA��肭�|����Ȃ�������@����������������A2�{�̔z�������ւ��Ă݂ă`�F�b�N����B�@�X�p�[�N���邪�^�C�~���O���قȂ邽�߁A�G���W�������܂����Ȃ��A���݂ɂ��̃G���W���́@��2�g(�}�C�i�X��)���_�^�C�~���O�̗l�ł̂ŁA�s�b�N�A�b�v�͐}�ʂƔ��Ɍq���ł��܂��B�@
|
�V�[�g�@���O��
 |
�V�[�g�@�^���N�@���O��
 |
����CDI ��H�}
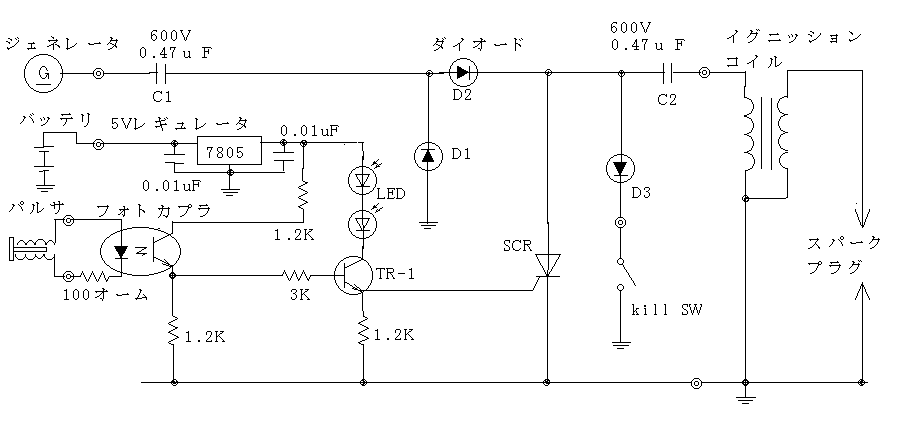 |
CDI ��H�}�̐���
�L�b�N�X�^�[�^���L�b�N���邱�ƂŁA���d�@�����@�T�OV�ȏ�̓d�����������āAC1�̃R���f���T��ʂ�A�_�C�I�[�h�Ő������ꂽ��AC2�̃R���f���T�ɏ[�d�����B
���̎��ɂ���ā@���d�@�̓d�����Q�{�ɂȂ�@��苭���d�͂�C2�̃R���f���T�ɏ[�d�����B
���ɁA�_�^�C�~���O�ɗ������A�r�b�N�A�b�v�@(�p���T)���A�𗬂̓d�C�������B
������A�t�H�g�J�v����ʂ��ďo�������g�̐M�����A�g�����W�X�^�ő������āASCR�̃Q�[�g��
ON�ASCR��ON�ɂȂ�A�A�m�[�h���J�\�[�h�ɓd��������AC2�̃R���f���T����d�A�R���f���T�ƒ���ɐڑ����ł���C�O�j�b�V�����R�C���ɒʓd�A�C�O�j�b�V�����R�C���̂Q�����ɍ����d���������āA�X�p�[�N�v���O�ɉΉԂ������B
���̂Ƃ��A�[�X�����v���X�ɂȂ�A�R���f���T�ƌq����Ă���C�O���b�V�����R�C�������@�}�C�i�X�ƂȂ�܂��B
�TV�̃��M�����[�^�́ASCR�́@�Q�[�g�ɂT�{���g�ȏ�̓d�����|���Ȃ��ׂƁA�g���K�[��H�����艻�������߂Ɏg�p���܂��B
�{�c����CDI �ƈ���ā@12V�d�����K�v�ł��̂ŁA�o�b�e���[����ł�����Ă��������BD3�̃_�C�I�[�h�̓L���X�C�b�`�ŃA�[�X�ɂȂ����ʼn�H���̂̓d�����OV�ɂ��ăX�p�[�N���~�߂�B
�t�H�g�J�v�����g�p�������R�́A�r�b�N�A�b�v�̋ɐ������R�ɕς����邱�ƂƁA�@�A�C�\���[�g���Ă���̂ŁA�������ƒ��ڐG��Ȃ����ƂŁA�s�b�N�A�b�v�̕ی��ړI�Ŏg�p�B
LED �́@�_�^�C�~���O�̓���m�F�ƁA�d���~���p�ŁA�Q����Ɏg�p���邱�ƂŁ@��3V���x�~�������B�@SCR�̕ی삪�ړI�B |
���̉�H�̓g���J�J��H��������H������Ă��܂���B�@
���g�������ꂽ�p���T�̐M���́@�㕔�̈ꕔ�����̂܂ܗ��p���Ă��܂��̂ŁA�K�v�Ȃ��Ɣ��f���č��܂���ł����B
�g���K��H�ɂ́@�R���f���T���g�p���Ă��܂���B����͎��萔�ɂ��x����Ȃ������߂ł��B
�@��]�������Ȃ�ɏ]���āA�e�����o��Ɣ��f���܂����B
�i�p�ɂ��ẮA�s�b�N�A�b�v�R�C���ɔ�������d�����A��]�ƂƂ��ɏ㏸���܂��̂ŁA��]���オ��A�g���K�̔����d��������܂�A���̕����i�p�ɑ������܂��B�ǂ̒��x���ʂ��o��Ă��邩�͕s���ł��B
�d��12V�����̉�H�ɂ͕K�v�ł����A�o�b�e�����オ��Ǝn���s�\�ł͂Ȃ��ł��傤��?�ƃ��[���ł悭���₳��܂��B
MTX125R�Ɋւ��܂��ẮA�o�b�e�����オ���Ă��Ă��L�b�N���̔��d�ŕ₦�܂��B
����CDI�@�ɕK�v�ȓd����8V�ȏ�ł����A�d����20mA���x�Ȃ̂ŁA�o�b�e�����オ���ăj���[�g���������v����_�����Ȃ��Ă��@�L�b�N�����Ƃ��A�j���[�g���������v�������ł��_������A(���d�@�����Ă��Ȃ�)
�G���W���͊|����܂��B
�]�k�ł����@����MTX125R��10�N�ȏ���o�b�e���[���オ���ςȂ��Ńo�b�e���̋@�\�͂���܂���B
�����Ł@�E�C���J�[�Ȃǂ̓d�������艻�������ׂɁ@�d���R���f���T22000uF����ɓ���Ă���܂��B
���̌��ʁ@�R���f���T���[�d����ԃX�p�[�N���x��܂����@�d���R���f���T22000uF���x�ł́A�[�d���Ԃ��@�����Z�����߁A�n���ɂ͖��͂���܂���B
|
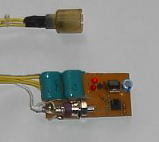
�z���_����CDI���@
���O�����R�l�N�^�[
��
����CDI ���
|
����CDI���P�[�X�ɓ���܂���
2�T�C�N��.�I�C���̃^���N��ƃV�[�g�̊ԂɁA�X�y�[�X������̂ŁA�����Ɏ��t���܂����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�}�E��)
|

���M�́@���g���悭������悤��
����Ă���܂��B
|
CDI�@�́@�W���C���g��
�R�l�N�^�[���@�^���N�̉��ɂ���̂ŁA���O�����A�^���N��E�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�V�[�g���܂Ł@�����o���܂����B
�����CDI�̃����e�i���X���ȒP�ɏo���܂��B |
 |
����CDI ���\�ƕ]��
�L�b�N�ꔭ�n��
���b�h�]�[���܂Ł@�X���[�Y�ɏ㏸�B
�I���W�i��CDI�@���n�������ǂ��B
���܂���̂ŁA�߂��ā@�P���@�͉�H�j���A�f�q�̑ψ��Ȃǂ�v�ύX�B
SCR�͓��� �r�e�W�i�y�S�V�Ȃǂł悢�Ǝv���̂ł����A���͎莝���̑�^SCR���������̂ŁA������g�����܂����B
SCR�̔��M���C�ɂȂ�̂ŁA���M�����t����K�v����B
�v���O�̏Ă�����@���肪�����ׂ��ǍD�ł��B
�]�@��
�W�T�_�ƌ����Ƃ���ł��傤���B
GOOD �ł��B
���R�����ā@�z���_���q���܌W��Ɂ@�ēxTEL���ā@������������`����ƁA
�悭�o���܂����ˁA�o����l�͏��Ȃ��ł���ƌ����Ă��܂����B
�ق�܂����ȁB
 |

����CDI�@���@���t���܂����B
���t���ăG���W�����|���Ă݂܂����B
�\���Ɏ��Ԃ��|����ꍇ������܂��B�@��1.5MB
|
���@�NjL�@���ǁ@�l�@�@�������ʁ@�� ����@�@�ŐV���Ȃ�
 �͂����� �͂�����
��H�@��R�@����
�s�b�N�A�b�v���̂P�O�O�I�[���̒�R�́AMTX125R�̏ꍇ�@3K�I�[���ł�����\�ł����B
3K�I�[���@���t���܂��ƁA���]��ł͂��ƂȂ����Ȃ�܂��B
���삷��ꍇ�A�s�b�N�A�b�v�R�C�������ނ�����悤�ł��̂ŁA�����d�����Ⴂ�܂��B�@�s�b�N�A�b�v�R�C���̓����ׂāA�s�b�N�A�b�v�R�C���ƒ����100�I�[���̒�R��ς���K�v������Ǝv���܂��B
�ȈՌ^�@�u�i�p�}����H�v?
���t�����^�]�������ʁA�m�[�}����MTX125R�ɖ߂�܂����B
�����̓s�b�N�A�b�v�̐M���̓d���̍����Ƃ���������A�^�C�~���O�M���Ƃ��Ďg�p���܂����B
���̌��ʁA����]�ƒ��]�Ƃ̐i�p�̍����������̂��A���̃��P�b�g�����͖����Ȃ�m�[�}���ɂȂ�܂����B
���@�͊ȒP�ALED 3��Ɍq���A�@�s�b�N�A�b�v�ƃt�H�g�J�v���̊Ԃɂ���邾���ł��B
�R���f���T�ɂ���
MTX125R�̏ꍇ�@�W�F�l���[�^���P��]�Ŗ�R�T�C�N����o�Ă���悤�ł��B
���������āAC1�̃R���f���T�̗e�ʂ́A�����Ə������e�ʂ̂��̂ł��ނ͂��Ȃ̂Ł@�O�D�PuF�ɂ��Ă݂܂����B
�n�����̊|�肮�����ɁA�e������悤�Ȋ����ł��B
�ق��́@�e���ɂ��ẮA�������Ă��܂���B
C1 C2�̃R���f���T�̗e�ʂŁA���\���ς��Ǝv���܂��B
�C�ɂȂ�T�C���X�^�̔��M
�����T�C���X�^�̓X�C�b�`���O����������A�قƂ�ǔ��M���Ȃ����낤�ƁA�v���Ă��܂������A�v�������A�T�C���X�^�͔��M���܂����̂ŁA���㔭�M��}����H�v�����Ă��������Ǝv���܂��B
���݂͕��M��t���Ă��܂��B
2006�N9��9�����M�̌����̓T�C���X�^�̑����������ł����B�����v���Ă����T�C���X�^�ƈႤ�������g�p�����̂��A�����̂悤�ł��B
�s�b�N�A�b�v�ɂ���
�s�b�N�A�b�v�͌𗬂������A�v���X�ƃ}�C�i�X�Ƒ��ɁA�P��]�ɂQ�ӏ��^�C�~���O���������܂��B
�z���_�̃T�[�r�X�}�j�A�����}�ʂɂ��ɐ������ɕ`����Ă���A
CDI���ŐM����I�����āA�g�p���Ă���悤�Ɏv���܂��B
�s�b�N�A�b�v�R�C�������ނ�����悤�ł��̂ŁA�����ׂĂ��������B
�i�p�ɂ���
���̉�H�ō̗p����Ă���i�p���u�́A�g�`�i�p����炵���ł��B
�W�O�N�㒆���܂ł̕��́A�A�i���O�d�q�i�p�Ƃ��Ă����炵���B
����̉�]���ɂ����Ă̂ݓ_�Ύ�����i�܂�����A�x�点����Ƃ���������͕s�\�ł���B
�g�`�i�p�̓s�b�N�A�b�v�R�C���̓����ɂ����̂������Ǝv���܂��B
|
�s�b�N�A�b�v�R�C���̔g�`

�@�@���̔g�`�̓l�b�g���
�@�@�q���܂����B |
�E�̔g�`�́A�s�b�N�A�b�v�R�C���̐M���g���������g�`�ł��B
���]���̃s�b�N�A�b�v�R�C���̔g�`�ƁA����]���̃s�b�N�A�b�v�R�C���̔g�`���ׂāA�Ԃ̖��̒������Ⴂ�܂��B
���ꂪ�g�`�i�p�ł��B
�Z���Ȃ������A�_�Ύ������i���ƂɂȂ�܂��B
|
�@�@�@�@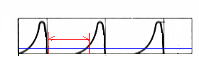
�@�@�@�@�@�@���]���̔g�`( �C���[�W)
�@�@�@�@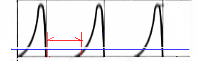
�@�@�@�@�@�@����]���̔g�`( �C���[�W)
|
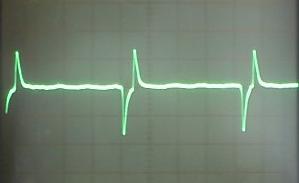
2V/DIV
5����/DIV
���� 40ms
1500������
��R�@82�I�[�����@�s�b�N�A�b�v�ɕ���ɓ�����
�C���s�[�_���X��������d��3V���x�����o�܂���
�@�m�C�Y���Y��ɏ����Ă��܂��B
���̏�ԂŎ��悵�Ă݂܂����B
�����オ�肪�@�����s���������܂��B
�����A�N�Z�����[�N�Ł@7000rpm�܂ʼn�������̂�5000rpm�ʂł����B
�m�C�Y�œ_�Ύ��������ꂨ����̏ꍇ
�������������B
�ǂ����ʂ��o��ꍇ������܂��B
|

2V/DIV
5����/DIV
���� 25ms
2400rpm
��R�Ȃ�
��]���グ�Ă݂܂����B
�r�b�N�A�b�v�̓d����6V�ɏオ���Ă��܂��B
|
|
�@�@�@�@ |
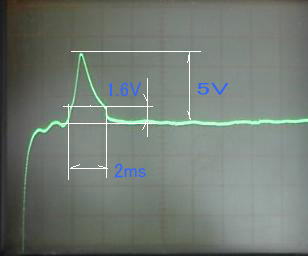
2V/DIV
2����/DIV
���� 40ms
1500������
2����/DIV�ɂ��ā@�������̂ł��B
����1.6V�t�߂ɕs�ψ�̕���������܂��̂�
�t�H�g�J�v�����I�������d���Ǝv���܂��B
����������1.5V�ȉ��̃m�C�Y�́@�t�H�g�J�v���ɂ����
��������Ă��܂��B
|
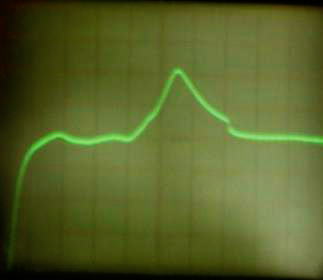
2V/DIV
1����/DIV
���� 40ms
1500������
1500�������ɂ�����
HT-ROCKET�̓t�H�g�J�v����ON���Ԃ���2ms��
18�x�ɑ������܂��B
|
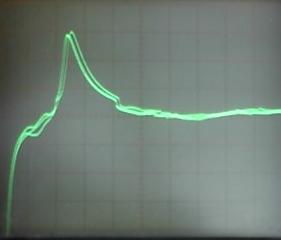
2V/DIV
1����/DIV
���� 25ms
2400������
�g�`��2�d�R�d�ɂȂ��Ă���̂�
�V���b�^�[�ԂɂQ����R��g�`���`���ꂽ�ׂł��B
�G���W���̔����Ȓx��i�߂�����Ă��܂��B
|
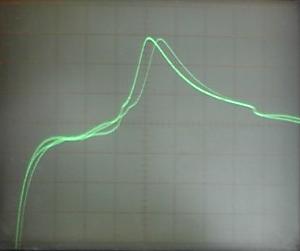
2V/DIV�@�@0.5����/DIV
���� 25ms�@�@2400������
2400�������ɂ�����
HT-ROCKET�̓t�H�g�J�v����
ON���Ԃ���2ms��36�x�ɑ������܂��B
��]���オ��Η��������肪�����悤�ł��B
|
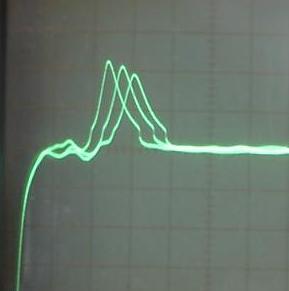
|
���}�@
���x�ɕω������������̂R��]���̔g�`�ł��B
�_�^�C�~���O���@�Z���Ȃ�@����Ɠ����ɓd�����オ���Ă���̂�������܂��B |
����CDI�����t����
MTX125R�̃s�b�N�A�b�v�g�`
�I�V���X�R�[�v���X�P�b�`�������̂ł��B
��1500rpm
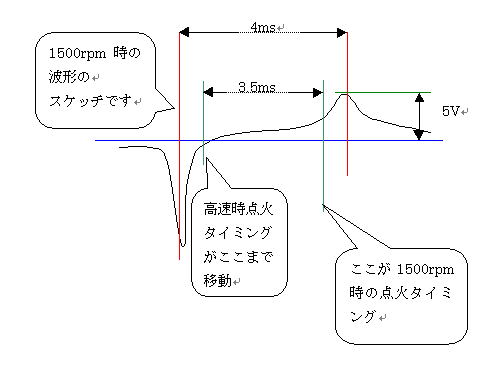 |
��1500rpm�Ł@����X�P�b�`���܂����B
��1�g�́@�}�C�i�X���Ł@�d����������2�g���_�^�C�~���O�ł��B
��1�g�Ƒ�2�g�Ƃ̊Ԋu��4ms�Ł@1500rpm�ł̊p�x�͖�36�K�ɑ������܂��B�@����]��ł́A�����d���̏㏸�ƁA��1�g�Ƒ�2�g�Ƃ̊Ԋu���k�܂�܂��B�@
��2�g�̓r���Ł@�t�H�g�J�v����ON���āASCR
ON �_�ƂȂ�܂��B
1500rpm/60s=25Hz
1/25Hz=40ms ����
4ms/40ms=0.1
360�x*0.1=36�x
|
�������̔g�`�̃X�P�b�`
��4000rpm
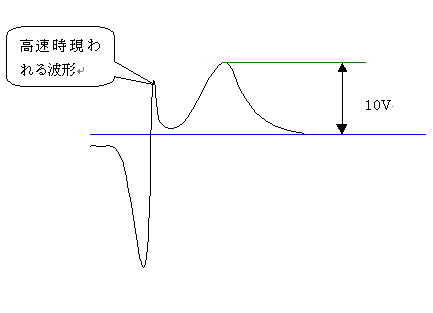
|
����]��ł́A��1�g�̏I���ɁA���]��ł͂Ȃ������g�`���o�����܂����B
�m�C�Y��������܂���B
���g�̕����̉s���g�`�́A�t�H�g�J�v���[�Ő��������P�O�O�I�[���̃C���s�[�_���X�ɑ��ĕ����͊J���[�ɂȂ��Ă��邽�߁A���̂悤�Ȕg�`�ɂȂ�܂��B
�������A���̉�H�ł́@�����̑��g�͎g�p���Ă��܂���B
�@
�NjL
2008/01/20
�ŋ߁A�������Ɍ���Ă����g�`���o�Ă��܂���B
�m�C�Y���e�ʐ������@�������Ă��邩���m��܂���B
2008/03/09
�s�b�N�A�b�v��2�{�̐��Ԃ�500�I�[���̒�R�������
�m�C�Y���ǂ��Ȃ�@���g�@���g�Ԃ́@�E�F�[�u�͂Ȃ��Ȃ�܂������A���g�@���g�Ԃ̓d����������܂��̂ŁA�g�`�i�p�ɉe���ł����ł��B
�܂����̉�H�̓t�H�g�J�v���[���g�p���Ă���̂Ł@1.8V�ȓ��́@�n�C�C���s�[�_���X�ɂ��I�V���ŕ\�����m�C�Y�́A������Ǝv���܂��B�@
�T�[�r�X�@�}�j���A������́@����ɂ��Ɓ@�i�p�ł͂Ȃ�
�x�p���@�̗p���Ă���l�ł���B
1300rpm BTDC19�x
6000rpm BTDC15.3�x
�x�p�n�߉�]��4000rpm
���̏��ʂ肾�Ɓ@���͂�1K�̒�R��0.1u�����Đϕ���H��t����Ύ����l�Ȓl���ł܂��B
�������@����͕K�v�����Ēx�p�ɂ����̂��@����Ƃ��m�C�Y��œ��ꂽ�R���f���T�̎��萔�̊W�Ł@�����Ȃ��Ă��܂����̂��́@�s���ł��B
�i�p����(�x�p)���u����L
|
�C�O�j�b�V�����R�C���@�P�����̔g�`

���̔g�`�́@�T�C���X�^��ON�������ɓ_�R���f���T�b2����
�T�C���X�^��ʂ��ăA�[�XE�ɗ����@�C�O�j�b�V�����R�C����
�ꎟ����ʂ�����ɓd���������B
���Ɉꎟ���R�C������A�[�XE��ʂ��ă_�C�I�[�h�c�P
D2�����
�_�R���f���T�b2�����ɓd�������݂ɗ���āA
�𗬔g�`����������B
�����ē��Ł@�����ɂȂ�ΉԂ�������B�@
|
- A �@���d�g�`�����܂ł̎���
- B �@���d�J�n�̏��߂́@�P�T�C�N��
- C�@ ���d�g�`�s�[�N�d��
- D�@ �Q�T�C�N���ڂ̃s�[�N�d��
�����܂ł̎���(A)�@200us 5�T�C�N��
�C�O�j�b�V�����R�C���@�ꎟ���R�C���ԓd��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@C�d�� �@�@D�d��
�@�@1500rpm �@�@�@200V�@�@�@ 100V
�@�@3000rpm �@�@�@300V
�@150V
�@�@5000rpm �@�@�@200V
�@100V
�@�@7000rpm �@�@�@150V �@�@75V
�@
�@��]���グ�Ă����Ɓ@��L�̗l�ɕω����܂��B
�@�����܂ł̎���(A)�@200us 5�T�C�N���͕ω��Ȃ��B |
�F�l����̐��@�ł��@�i�f���ɃJ�L�R���ꂽ���̂��܂Ƃ߂����̂ł��B�j
2007.9.3�@HP�����J���Ė�P�����@���߂Ă̐������܂����B
��������̃C���v���b�V�����@�@
���}�n�@�q�c�S�O�O�p�ɐ��삵�܂����B
�@�������[�[�H�H�H�I�I�I���Ǝv���قǂɁA�������Ȃ��G���W���|����܂����I�I�i���j
�т����肵���Ȃ��[�����[�I��ނ��o���Ȃ̂ŁA�܂������Ă͂��܂��u���b�s���O���������ł͖�薳�������オ��܂��B
���s���Ă݂ĂQ�O�O�O��]�ł̃M�N�V���N������
�q�c�S�O�O���ᑬ�`���[�W�R�C���@�����`���[�W�R�C������@�����`���[�W�R�C�������g�p���Ȃ������B
������ᑬ�`���[�W�R�C������̔z�����]�Ă����̂ŃR���f���T�ƃ_�C�I�[�h��lj����Ēᑬ�`���[�W�R�C������̕������ɂ��A�T�C���X�^�Ɍq���Ă݂܂���
�����ł��B���喳���ł��B�����ł��H�H
���}�n�@�q�c�S�O�O�p�ύX��H�͂�����
�Q�O�O�O��]�̃M�N�V���N�������A�m�[�}���b�c�h�����t�B�[�����O�Ɋ��܂ł��i���j
�M���Ŏ~�܂�ƁA�A�C�h�����O�����肵�Ă��܂��B���������]�������Ĉ��肵�Ă���B
���ׂ̍������C���ǂ�����������ƃO�[���ƐL�т�B
������Ə���������ł��m���ɑS�̂����サ�Ă��܂��B
�Q�O�O�O��]����ł��g���N���o�n�߃A�N�Z���ɉ�]���t���Ă���̂ɂ͊������܂����i�j
����̐����͊Ǘ��l�l�̉�H���\���Ȕėp�������邱�Ƃ������Ă��܂�
�킸�������Ԃ̊Ԃɂ����܂ł̌��ʂ��o����Ƃ͎v���܂���ł����B
�T�C���X�^�̔��M�̌��ł����A���M�����ɏ��P���Ԃقnj��C�ɑ����Ċm�F�����Ƃ���A�܂������M���Ȃ��Ă��܂���ł����B
�b�P�A�b�Q�̃R���f���T�A�O�[�q���M�����[�^�[���ꂼ��w�ŐG���Ă��܂��������v�ł��B
���̂b�c�h�łQ���ԂŖ�U�O�Okm�i�����A�����̎R�A��ʓ��j���薳�������Ă���܂����B
���̌�̃C���v���b�V�����������Ă����܂��̂ŁA�������l�����Ăb�c�h�Ƀ`�������W���Ă��������B
�q�c�ɂƂ��āA�ǂ�ȃp�[�c�������͂ł��B
���q�����ď��Ă�����A�G���W���̕����w�^�������ɂȂ��Ă��܂����i�j
��]�㏸�������Ȃ��ăp���[���o�镪�A�G���W���ւ̕��S���傫���Ȃ�܂��B
�}���ȃ����e�i���X�Ɗ�{�I�ȃZ�b�e�B���O���o���Ă��Ȃ��ƏĂ��t���͕K�����Ɓi���j
�܂��A�O�̂��߂Q�X�g�I�C���͍����ȕ����B
�O��u���[�L�͊m���ɍ쓮����悤�ɁB�������ǂ��Ȃ�X�s�[�h���オ��̂ŁA�u���[�L�̌������Â��Ǝ��̂Ɍq����܂��B
���x�}�����u�������̋C�����̒��ɑg�ݍ��ނ��Ɓi���j
�R���f���T���@���낢��ς��Ď������܂����B
�Q.�QuF�ł��\���ł����i�P.�OuF�ł����ʂɑ���邵�j�R.�P�S���e�ł� ����Ƀg���N�������Ȃ��ăG���C���ƂɂȂ��Ă܂��i�j
�^�R���[�^�[�̐j�̏オ������m�[�}���ł͗L�蓾�Ȃ����������܂����i�j
�����ǁA���̕��N�����N�ɕ��S���|�����Ă���̂��Ǝv���ƁA���̕ӂł�߂Ă����������C�C�̂��ȁH�Ǝv���܂��B

���}�n�Q�T�C�N���o�C�N��RD SURVIVE�@���������HP�͂�����
|
H����́@�C���v���b�V����
���}�n�@�q�c�Q�T�O�p�ɐ��삵�܂����B
�g�s�|�q�������������^�b�p�[�ɂ߂Ďԑ̂ɂȂ��ŃG���W���������Ă݂�ƁA������O�̂悤�ɂ������肩����܂��B
�����Ă݂�ƁB�B�B�ᑬ���炵������g���N���o�āA���̂܂܂����������Ő����������Ă����܂��B
�����Ԃ̂q�c�Q�T�O�͂قƂ�ǃm�[�}���Ȃ̂ł����A�ᑬ�����܂����������̂łނ�����₷���Ȃ��Ă����ۂł����B
�听���ł��I
�m�[�}���Ƃ̃p���[�̈Ⴂ�ɂт�����ł����A�Ȃɂ��d�q�H�쏉�S�҂̎������������H�ő����Ă��܂������Ƃɂт�����ł��I
�ȈՌ^�i�p�}����H��ւ��X�C�b�`�t����t���Ă݂܂����B
�k�d�c���R�t���ăX�C�b�`��t���āA�n�m�A�n�e�e�A�n�m�Ȃ̂ŁA���܂����n�m�͂Ƃ肠�����k�d�c�P�ڂɕt���܂����B
�ԑ̂ɂȂ��ŃG���W���n���I���������������B
�܂��͂k�d�c�R�ő���o���Ă݂܂����B
�G���W���̂�����͈��������ŁA������ƃA�N�Z����������Ȃ��Ƃ�����Ȃ��A
�v�����قǒᑬ�������Ȃ��Ă��Ȃ��悤�����A����������͌����ɂQ�i���P�b�g�I
�̊��I�ɂ͂ނ��낱�����̕��������̂ł́H�Ɗ����Ă��܂��B
���ɂk�d�c�P�B
�G���W���̂�����͂�����ƈ������Ȃ��Ƃ��������B
�����Ă݂�ƁB�B�B���`��A�悭�킩��Ȃ��Ȃ��Ă����B
�ǂ��炩�Ƃ����ƃ��P�b�g�ɋ߂��������Ǝv���̂ł����A��肷���Ă����킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
�Ō�Ƀm�[�}���b�c�h�B
���`�A����ς�m�[�}���ɂ���ƑS�̓I�Ƀg���N����������Ɣ����悤�ȁc
 |
RZ�@�ɏ���Ă���@K����́@�C���v���b�V����
�f���炵���b�c�h�ł��ˁE�E���b�`�����ꍞ��ł��܂��܂����B
�R���f���T�@�O�D�S�VuF�ƂQ�D�OuF�łQ��ލ��e�X�g���܂����B
�R���f���T�@�O�D�S�VuF�ƂQ�D�OuF�̈Ⴂ�ł����u��������I�ӌ��ł��v
�Q�D�OuF�̕����@�ᑬ���S�R�ǂ��ł��ˁE�E�����q�y���@�U���u�g�b�v�v
�P�T�O�O��]�Ŕ��i�\�ł��u�O�D�S�VuF�v���f�R�ǂ��ł���
�p���[�o���h���T�O�O�O����m���ɗ��܂��E�E�E�E�u�O�D�S�VuF�����܂����@������ǂ��ł��v�@�@�R�O�O�O��]����������p���[�o���h������������ł��B�@�u�m�[�}������Ηǂ��ł��ˁE�E���ɂ͖߂�܂���v
�uRZ���X�N�[�^�[�ɂȂ��Ă��܂����ȁH�H�v
���̂b�c�h���@�S�����ɗL������@�q�y����������������L���������H�E�E�E�E
���s�e�X�g�@�X�s�[�h�I�[�o�[�e�X�g�͏o���܂��E�E�E
�Ȃ�@�P���łT�O�O�O��]����X�T�O�O��]��p�Ł@�R�O���ԑ��s���Ă݂܂����@�����x�v���W�T�x�O��ň��肵�Ă��܂����@�@�����@�R�C���̉��x���O�C���x��葽���������x�Œ��q�ǂ��ł�����CDI�����݂ł�
�v���O�͋C�����@�ϐF���ȁE�E�E���b�`�����q�����ł��B
�u���W�G�^�[�̑O�ɑ����ڒ��肵�āv
���̂q�y�͂قڃm�[�}���ł��@�@�s�X�g���ɏ������H���Ă��邮�炢�B
�g�p�ړI�́@���c�[�����C���ł����E�E�E�E�u�����͂قڂ��܂���v
CDI �̃T�C�Y�́u�O�D�S�VuF�łV�p�S�p�Q�D�T�p�ō��܂����@�Q�D�OuF�ł��@����Ȃɑ傫���͗L��܂���B
|
�Z���[�i�QLN�j�@�ɏ���Ă���@S����̕�
�莝���̃Z���[�́A�ǂ����CDI�̃p���N�炵��
�Ƃ肠�����A�I���W�i��HT-ROCKET��H�őg���
��������G���W����������܂����B
�i���\��������ł��˂��I
�����A����]��H�����܂���B
�i�����Ă���悤�ł��B���܂��Ƀ^�R���[�^
���Ȃ��̂ŁA����]����`�Ƃ������ł��Ȃ��̂��c�O�j
����Ƃ��A�S�T�C�N��������@����CDI�Ɓ@�}�b�`���Ȃ��̂��ȁE�E�E
�ƌ������Ł@�i�p����t���@�f�W�^��CDI����Ɂ@���퐬�����܂����B
�ڂ����́@������ |
RZ250�@�ɏ���Ă���@T����́@�C���v���b�V����
��S�O�O�L���̓��A��c�[�����O�ł������A�m�[�g���u���ŋA���Ă��܂����B
�҂����킹�ꏊ�������C���^�[����T���ʂ̃T�[�r�X�G���A�������̂ŁA�ꑫ�����s���v���O�`�F�b�N�����Ƃ���A����܂ł̓J�[�{�����t�����������d�ɂ��Y��ɏĂ��A�قƂ�ǃJ�[�{�����Ă���Ă��܂����B
�܂��A�ŋߋC�����オ���Ă����̂ŁA�����悪�����Z���悤�Ȋ����Ńo���o���ƃJ�u���C���������̂��p���p���Ƃ������C�ȉ��ɕς���Ă��܂����B
���̂q�y�͂Q�X�g�A�`�����o�[�t���Ȃ̂ŁA���܂ł͍����̂U���P�O�O�`�P�P�O�L�����q�ł͎������Ă��āA���̂��тɂQ�����炢�V�t�g�_�E�������đ��x�ɏ悹��Ƃ������G���W���ł������A�Ȃ�Ƃ����x�ێ����ł��A�ނ�݂₽��ȃV�t�g�_�E��������A������̔S�肪�o���悤�Ȋ����ł��B
����]�ł͋z�C�����傫�������ɕς��A�g���N�͂��̂܂܂ŐU�������Ȃ��Ȃ�A�y������ۂ������܂����B
�傫��������̂��A�R�����Ԕ�������Ƀm�[�}���b�c�h�͂U�T�O�O��]����̃p���[�o���h���V�O�O�O��]����ɂȂ��Ă��܂��A�p���[�o���h���T�O�O��]���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A�G���W�����̔M�̊W���Ǝv���Ă��܂������A���ꂪ�����Ȃ�A�t�ɂU�T�O�O��]���O���Ă��܂��Ă��A�N�Z�����J���ď����҂��Ă���ΐ����オ���Ă��܂��B
�܂��A���܂ɃM�A�������N�����̂ł����A���܂ł̓M�A�������N�������u�ԂɃ^�R���[�^�[������ƂP�Q�O�O�O��]�ʉ���Ă����̂��P�S�O�O�O��]������Ă��܂����i���j
�R������҂ł��邩�Ǝv�����̂ł����A�S�s���̂قƂ�ǂ����C���f�B���O�������̂ŕς��Ȃ������ł��B�i������̖��I�I�j
�b�c�h�̎d�l�̓R���f���T�[�͂R���@�O.�S�Vu�e�~�Q�̂O.�X�Su�e���q�c�S�O�O�p�ō��܂����B
���̂悤�Ȋ����Ő�D���Ȉ���ł����B
�m�[�}���b�c�h�ً͋}���ׂ̈Ɏ��t�����܂܂ł����A�����m�[�}���ɖ߂��C�͖����ł��B
�����Ŕ�r�I�ɊȒP�ɍ��A�������m�[�}�������m���ɐ��\���ǂ��A���̂Ƃ���f�����b�g�͌�������܂���ł����B
�������������ۂ��ȒP�ł����A�����Ă��������܂��B
|
���삪�m�F���Ă���@�o�C�N�̋@��
�̂��������̂L�ڂ��Ă��܂��B
| ���[�J |
�o�C�N�� |
�`�� |
�G���W�� |
�N�� |
�s�b�N�A�b�v�d�� |
����
��R |
�����R |
���� |
�R���f���T |
�A�h�o�C�X �@�@���@���@�@���z |
| �z���_ |
MTX125R |
. |
����2
�T�C�N�� |
1982 |
�}�j�A���ł�0.7V�ȏ�
|
���� |
100�� |
�ǍD |
1�ʂe |
0.47uF����@1uF��2�Ƃ����ւ�
���ʁ@���₷���������悤�ł��B�S��Ƀp���[������悤�Ȋ����ł��B |
| �z���_ |
XL125R |
MD06���� |
4�T�C�N�� |
. |
0.7�u |
. |
32�� |
�ǍD |
2.2�ʂe |
�ᑬ�ł̃A�N�Z���̃c�L���ƂĂ��ǂ��ł� |
| ���}�n |
���[�h90 |
HF05 |
2�T�C�N�� |
. |
.�d�������܂薳���悤�ȋC�����܂��B |
����. |
100�� |
�ǍD |
1�ʂe. |
�m�[�}���Ƃ͔�ו��ɂȂ�Ȃ����ᑬ�̃g���N���o�܂����B
�s�b�N�A�b�v�R�C���̓d�������܂薳���悤�ȋC�����܂��B |
| ���}�n |
�i�n�f��
���� |
�Q�i�`�^�� |
2�T�C�N�� |
. |
. |
�T�O�� |
100�� |
. |
. |
. |
| ���}�n |
�i�n�f |
�S�����^�� |
2�T�C�N�� |
. |
. |
100�� |
. |
. |
. |
. |
| ���}�n |
�W���O�A�v���I |
�SJP7 |
2�T�C�N�� |
. |
���茋��
�m�[�}��CDI���t�����@4500rpm��
56V |
��
��R
�R�P�O�� |
. |
�ǍD |
1�ʂe |
�s�b�N�A�b�v�ɕ���Ƀ_�C�I�[�h�Ɖϒ�R�g�ݍ��킹�����ł��B
�g���N���@�����@�ō���]���̐L�т��A���ɗǂ��Ȃ�@�ő��̓��[�^�[���U��ꂽ����������Ă���悤�ł��B
|
| ���}�n |
�i�n�f�X�O |
. |
2�T�C�N�� |
. |
. |
100�� |
. |
�ǍD |
. |
����͂k�d�c�A����i�T���炢�j�ŏǏ����܂����A����������R���n�����Ȃ킸�D���ʂł��B |
| ���}�n |
�W�O�n |
. |
2�T�C�N�� |
. |
.. |
. |
. |
�s�� |
. |
�s�b�N�A�b�v����肭�����Ȃ��B |
| ���}�n |
TZR50 |
. |
2�T�C�N�� |
. |
. |
. |
. |
�s�� |
. |
�f�W�^���̂��� |
| �X�Y�L |
RG250
�K���} |
. |
����2
�T�C�N�� |
. |
. |
100�� |
100�� |
�ǍD |
C1������C2��
2.2��F |
�ΐ����_�C�I�[�h�̃J�\�[�h�Ɍq���ŃA�[�X�ɗ��Ƃ��Ă�
���[�J�}�j�A���ʂ� |
| �z���_ |
�X�y�C�V�[�P�Q�T |
�i�e�O�R |
����
4�T�C�N�� |
. |
. |
. |
. |
�ǍD |
�O�D�S�V�� |
.���M�����[�^�i�G�L�T�C�^�R�C���j����ꂽ�̂ŁA�[�d�p�̃��M�����[�^�i�O���𗬁j����d�������o���A�K���ȃg�����X�P�O�O�u�|�U�u�P�`���x���炢���������̂ŁA����ɐڑ�������v���O�ɉΉԂ���̂ŁA�����Q�O�����قlj����ɑ���܂����B
|
| ���}�n |
�q�c�Q�T�O |
. |
2�T�C�N�� |
. |
. |
���� |
100�� |
�ǍD |
. |
��H�q�c�S�O�O�p�@�@�C���v���b�V�����w |
| ���}�n |
RD400 |
. |
2�T�C�N�� |
. |
. |
���� |
100�� |
�ǍD |
2.2�ʂe |
��H�q�c�S�O�O�p�@�@�C���v���b�V�����w |
| ���}�n |
�qZ�Q�T�O |
. |
2�T�C�N�� |
. |
. |
���� |
100�� |
�ǍD |
1�ʂe |
�C���v���b�V�����w |
|
|
|
|
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
| ���}�n |
RZ250R |
. |
����2
�T�C�N�� |
. |
. |
����. |
100�� |
�ǍD |
1�ʂe |
http://www.cafe-costa.com/rz.html
http://www.cafe-costa.com/userfiles/image/rz/cdi.jpg
|
| �z���_ |
NS50F |
. |
����2
�T�C�N�� |
1989 |
. |
���� |
100�� |
�ǍD |
. |
�s�b�N�A�b�v�ƃt�H�g�J�v���̊Ԃ̒�R�͑傫�߂ɂ����ق���������������܂���B
�������Ɠ_�Ύ��������������悤�ł����B
|
| ���}�n |
�qZ�Q�T�O |
. |
����2�T�C�N�� |
. |
. |
���� |
100�� |
�ǍD |
2.2�ʂe |
�R���f���T�@0.47uF���@2.2uF�̕����ǂ��@
��H�q�c�S�O�O�p�@�@�C���v���b�V�����w |
| �z���_ |
�X�[�p
�J�u90 |
�g�`�O�Q�|�Q�T�O�O |
���4�T�C�N�� |
2001 |
. |
.���� |
100�� |
�ǍD |
�P�D�T�ʂe |
�m�[�}���ɔ�ׂčō���]���͕ω��L��܂���
�m�[�}�������ǂ������ł� |
| �z���_ |
�m�r�q�T�O |
. |
����2
�T�C�N�� |
. |
. |
. |
. |
�ǍD |
2.2�ʂe |
. |
�@�@�@�@*�@�����R�@�@�s�b�N�A�b�v�ɕ���ɒ�R������R �W���ł͖���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s�b�N�A�b�v�ɕ���ɒ�R�����Ɓ@�C���s�[�_���X����������g�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���g���ɓd���~�����邽�߁A�m�C�Y�ጸ�ɂȂ���B
�@�@�@�@
�@�@�@�@*�@�����R�@�@�s�b�N�A�b�v�Ɓ@�t�H�g�J�v���ԂɁ@����ɓ����Ă����R�@�W���ł�100��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�傫������Ɓ@�n������ɂȂ�B
|
�ύX�@�C��
2008�N2������CDI��H�́@C1 C2�̃R���f���T���@0.47uF����@1uF��2�Ƃ����ւ�
���ʁ@���₷���������悤�ł��B�S��Ƀp���[������悤�Ȋ����ł��B
������̕��������߂����m��܂���B
�ŐV���
2009/09/14
�_�Ύ���������]�ŗ����ꍇ�@�s�b�N�A�b�v�ɕ���ɒ�R�����B
��R�����Ȃ��ꍇ�@�m�C�Y�������_�^�C�~���O�������B
�s�b�N�A�b�v�ɕ���ɒ�R�����Ɓ@�C���s�[�_���X����������g�@���g���ɓd���~�����邽�߁A�m�C�Y�ጸ�ɂȂ���B
�G���W���_�ΐ���ɂ�����_�Γ��������シ�邽�߂ɂ́A�C�O�j�b�V�����R�C���̈ꎟ�C���_�N�^���X��傫�����ĉΉԂ̎������Ԃ�����Ȃǂ̕��@������Bhttp://www.patentjp.com/08/O/O100163/DA10016.html ���
|
����������ǂ��_�@�K�b�e���̂����Ȃ��_ ��肭�����Ȃ��@�ȂǗL��܂�����E�E�E�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�f���� �܂� �܂�
�܂��ŐV���@������Ă��܂��̂ŁA�@���삳���ꍇ�́@�K�������������B
�����x�����߂Ă��������Ǝv���Ă��܂��̂ŁA�ǂ�ǂ�@��������ł��������B
|
 �@����CDI�삵�ā@�������ʂȂǂ����J���ĉ������Ă���T�C�g �@����CDI�삵�ā@�������ʂȂǂ����J���ĉ������Ă���T�C�g
 ���ӎ��� ���ӎ��� 
���d�ɒ��ӂ��Ă��������B
�X�p�[�N�v���O�̕��d�Ŋ��d����ƁA���ɂ�����邱�Ƃ�����܂��̂ŁA���ꂮ����A�X�p�[�N�u���N�J�ɐG�ꂽ�܂܁A�G���W�����|������A�L�b�N�X�^�[�^�܂Ȃ��ł��������B
�R���f���T�ɂ��@�d�C���~�����Ă��܂��̂ŁA�ʓd��@�d�C����Ă��Ă��A���d���邱�Ƃ��@����܂��̂ŁA�@�R���f���T����d��������ɐG������A���d�̊댯�͂���܂���B
�R���f���T����d���@�́A�R���f���T�̗��ɂ��@�V���[�g�������OK�ł��B
|
�Ɛ�
���ȐӔC�ł��肢���܂��B
���̎������ʂł��̂ŁA�S�Ăɂ�������肭�����ۏ������̂ł͂���܂���B
�ԈႢ�����邩������܂���B
���̏��Ɋ�Â��Ĕ���������Ȃ鑹�Q�ɂ��Ă��A
�����́A��ؐӔC�����˂܂��B
���쌠
�����N�͎��R�ł���
HP ��H�Ȃǂ̒��쌠�͕������Ă��܂���B
�l�Ł@���삵�ā@�y���ޕ��Ɋւ��Ắ@����K�v�Ƃ��܂��@�����������Ɗ������ł��B
�c�ƂȂǂŗ��p�����ꍇ�́@�A�����肢���܂��B
|
���̃z�[���y�[�W�� �ւ��邲�ӌ���
�����������������B
�摜��Up�@Load �o���܂��B

�f �� ���@
|

|

�^�C�����[�ɍX�V���Ă��܂��B�����X�V������A
�ق����炩�����L��܂��B
�C�܂���J���X���J�����ׁ̈@
���������ŕs�e�Ɂ@�����Ă���܂��B
����������Ό��Ă��������B |

�@�@By Hajime tanaka
|